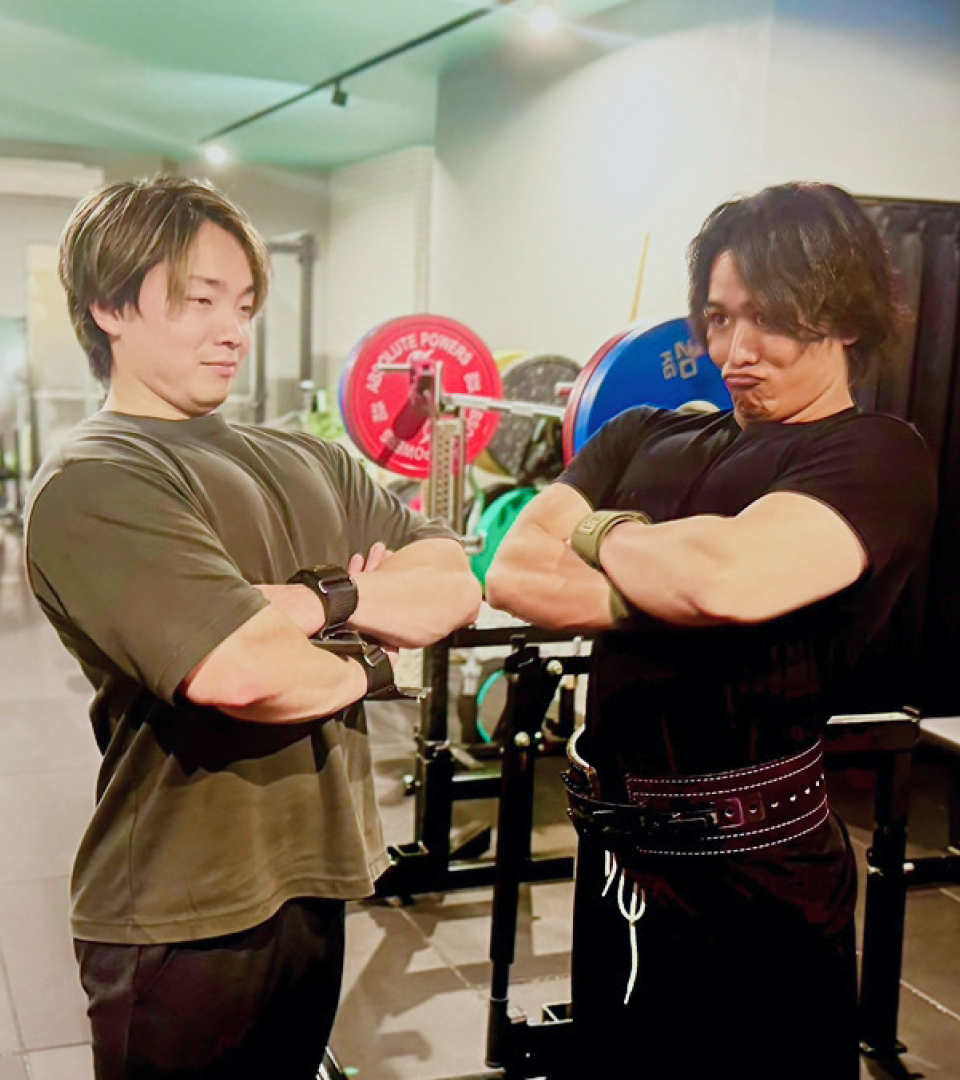2025.04.12
夜ご飯を抜くと本当に胃腸が休まるのか

こんにちはTOMOAKIです。
今回は、クライアントさんやSNS上でもよく耳にするテーマ
「夜ご飯を抜いて胃腸を休めたほうがいいのか?」について、
論文をもとに整理していきます。
結論から言うと、
「胃腸を休める目的で夜ご飯を抜く必要はない」と考えられます。
むしろ、状況によっては筋分解や代謝の低下、
睡眠の質の低下といったリスクがあることが報告されています。
1. 胃腸は“休ませる”べき器官ではない
「夜ご飯を抜いて内臓を休めたほうがいい」という意見もありますが、
医学的には胃腸は“休ませる器官”ではありません。
食事は、消化酵素の分泌や腸のぜん動運動を促し、
胃腸の機能やリズムを整えるために重要な刺激となります。
また、食事のタイミングは体内時計(概日リズム)にも関与しており、
規則的な食事が消化器の機能維持と健康な代謝に寄与すると報告されています。
参考文献:
Adverse metabolic and cardiovascular consequences of circadian misalignment
2. 空腹時間が長いと筋分解が進む可能性
長時間の絶食が筋肉に与える影響を示す研究では、
60時間の絶食によって筋肉からのアミノ酸放出が2〜3倍に増加したことが報告されています。
参考文献:
Effect of starvation on human muscle protein metabolism and its response to insulin
もちろん、夜ご飯を1回抜いただけで極端な筋分解が起こるとは限りません。
しかし、空腹状態が長時間続くことで筋タンパク質分解が促進される可能性がある点には注意が必要です。
特に筋量を維持したい方や、減量中の方にとっては無視できないリスクです。
3. 睡眠と食事のリズムは密接に関係している
軽度の空腹感は入眠を促すこともありますが、強い空腹感は中途覚醒の原因となり、
睡眠の深さや持続性を低下させる可能性があるとされています。
また、空腹が強いと交感神経が優位になりやすく、
リラックスしづらくなる=寝つきが悪くなるといった傾向も指摘されています。
食事の時間は、体内の周辺時計(peripheral clock)を調整する重要な要素です。
食事のタイミングが乱れると概日リズムが乱れ、
メラトニンなどの睡眠ホルモンの分泌に影響する。参考文献:
Adverse metabolic and cardiovascular consequences of circadian misalignment
つまり、夜ご飯を極端に遅らせたり抜いたりすることで、
体内リズムが乱れ、結果として眠りにくくなる可能性があります。
空腹が続くと、食欲抑制ホルモン「レプチン」が低下し、
食欲増進ホルモン「グレリン」が増加します。
この状態に加え、睡眠時間が短くなると、さらにホルモンバランスが崩れることが示されており、
翌日の過食やジャンクフードへの欲求増大につながる可能性があります。
夜ご飯を抜く → 空腹状態で寝る → 睡眠の質が悪化 →
ホルモンバランスが崩れる → 翌日食欲が増加 → ダイエットに逆効果
という負の連鎖が起きる可能性があるため、
「空腹で眠ること=健康」とは必ずしも言えないことが分かります。
4. 食事パターンの乱れは代謝を下げる
食事時間が不規則になることで、
食後のエネルギー消費(TEF: Thermic Effect of Food)が低下するという報告もあります。
夜ご飯を抜くことによって、1日の食事リズムが乱れると、
代謝全体が低下する可能性も否定できません。
まとめ
胃腸を休めるという目的で夜ご飯を安易に抜くことは、
代謝・筋肉・睡眠・ホルモンなど多方面にリスクがあるといえます。
特定の病態(例:機能性ディスペプシア)を除けば、
「抜く」のではなく、「量や内容を整える」ことが現実的かつ効果的です。