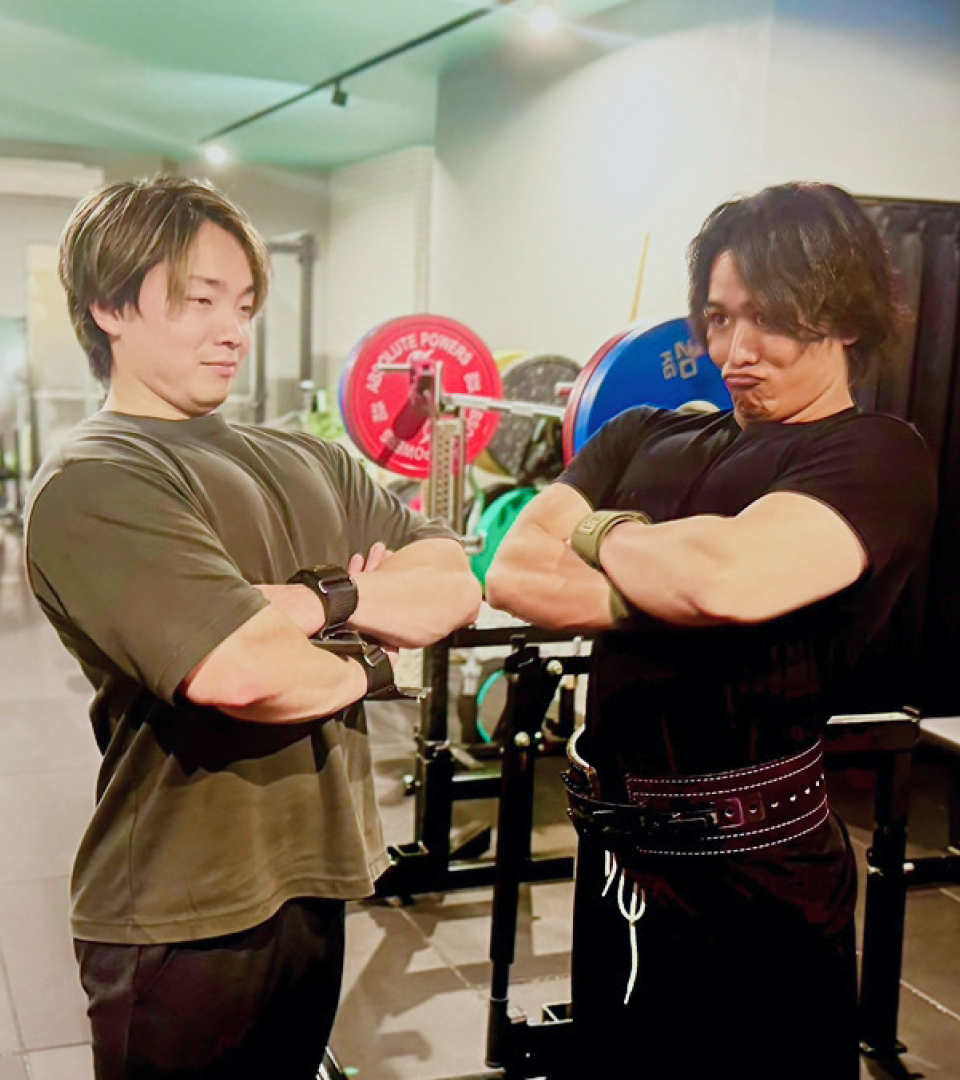2025.03.23
空腹でなくてもつい食べちゃう?
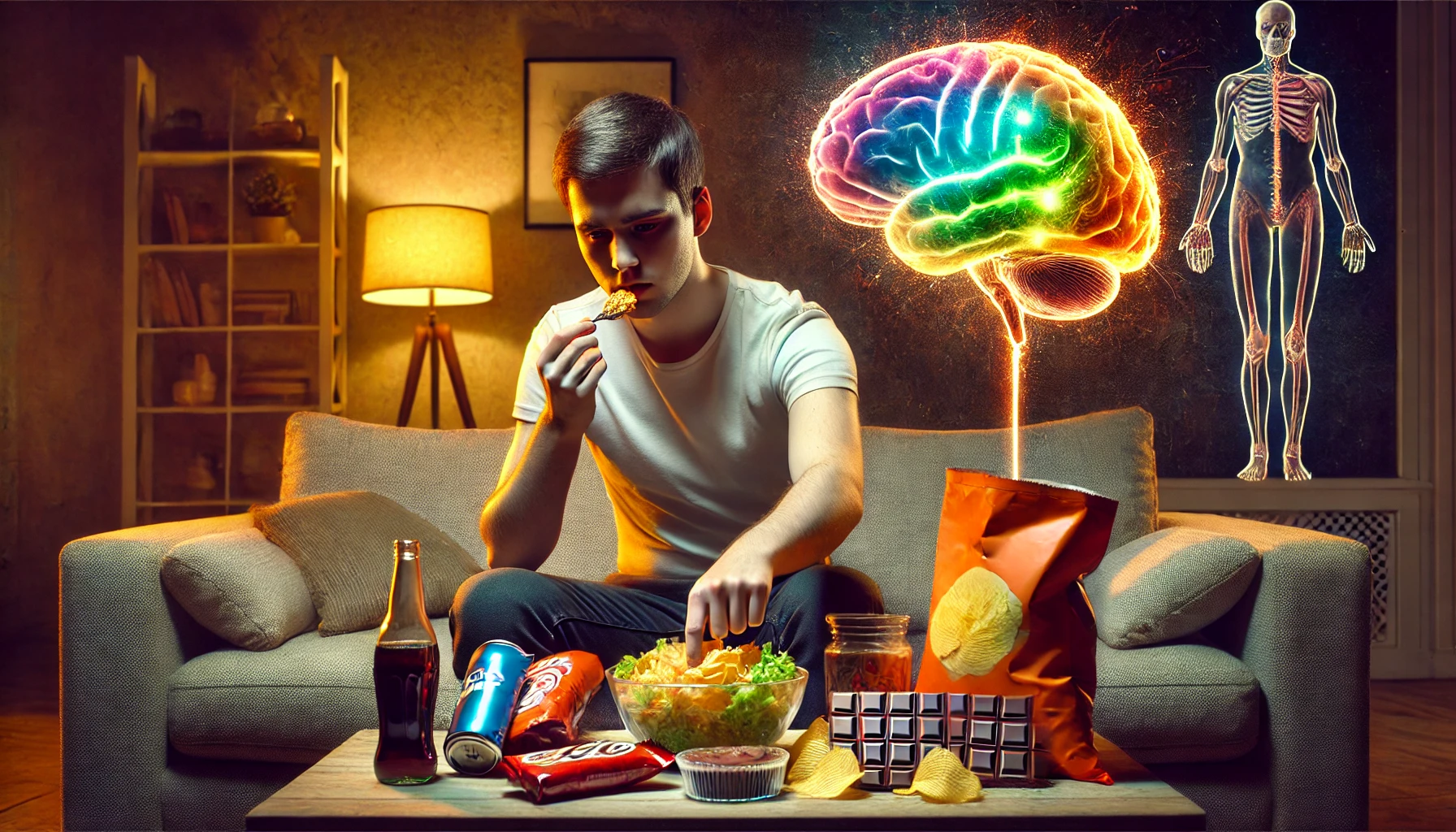
こんにちは、TOMOAKIです。
オンラインコーチングやパーソナルトレーニングの現場で
よく受けるご相談のひとつに、
「お腹が空いていないのに、ついお菓子やジャンクフードを食べてしまう」
というものがあります。
このような衝動は、減量中の方や
体型維持をしている方にとっては、非常に悩ましい問題です。
実は私自身も、減量後や大会明けのように
エネルギー状態が安定しているにも関わらず、
甘いものや脂っこいものを欲してしまうという経験がありました(汗)。
この「空腹でないのになぜか食べたくなる」という衝動、
2023年の神経科学研究によって、
“脳の報酬系”が深く関わっている可能性が示唆されています。
本記事では、2023年に発表された臨床研究
「Habitual daily intake of a sweet and
fatty snack modulates reward processing in humans」の内容をもとに、
高脂肪・高糖質の食品が脳にどのような影響を及ぼすのか、
過食行動を引き起こしうる神経的メカニズムについて、
科学的に解説いたします。
参考文献:
Habitual daily intake of a sweet and fatty snack modulates reward processing in humans.
「満腹でも食べたくなる」は脳の変化?
本研究では、正常体重の成人を対象に、
8週間にわたり以下のいずれかのスナックを
1日2回摂取するというランダム化対照試験が実施されました。
- 高脂肪・高糖質(HF/HS)スナック群
- 低脂肪・低糖質(LF/LS)スナック群
それ以外の通常の食事は自由とし、
体重や代謝指標には大きな変化がないことを確認しつつ、
脳活動と味覚・嗜好の変化を観察しました。
主要な研究結果
1. 脳の報酬系が強く反応するようになる
「HF/HSスナックを8週間摂取した群では、
低脂肪食品の好みが減少し、ミルクセーキ(高脂肪・高糖質)の
摂取に対する脳の反応が増加した」
- 中脳(腹側被蓋野、黒質)や前頭前野、島皮質、視覚野などで、
ミルクセーキの予告と摂取に対して有意に高い反応が観察されました。 - この変化は体重の変化を伴わず、純粋に「食事内容」による影響とされています。
2. 報酬学習の神経機構が強化される
「HF/HS摂取後には、食とは無関係の報酬学習課題においても、
学習シグナル(予測誤差)の脳活動が強まった」
- 腹側線条体、海馬、前頭前野などの領域で、
報酬に関する神経活動が顕著に増加しました。 - このことは、単なる「食べ物への欲求」だけでなく、
脳の学習や動機づけ全般に変化が及ぶ可能性を示唆しています。
3. 味覚の感知能力には変化がないが、好みに変化が起きる
- 味の「脂っこさ」「甘さ」を感じ取る能力自体は変わらなかった一方で、
HF/HS摂取群では低脂肪食品への「好み」や「欲しさ」が有意に低下しました。
ダイエットや食事管理への示唆
本研究は、「満腹なのに甘いもの・脂っこいものが欲しくなる」
という現象の背景に、脳の報酬系の可塑性(変わりやすさ)が
関与している可能性を示しています。
- 高脂肪・高糖質食品を継続的に摂るだけで、
低脂肪食品の好みが減る。 - 食品に含まれるカロリーではなく、
その構成(脂質と糖質の組み合わせ)が脳への影響を及ぼす。 - これらの変化は体重が増えなくても起こる。
まとめ
本研究は、「わずか8週間の高脂肪・高糖質スナックの習慣的摂取」が、
体重や血糖値などの代謝に変化がなくても、脳の報酬系を再構築し、
嗜好や学習の仕組みに影響を及ぼすことを明確に示しました。
特に注目すべきは、「食べ物の好み」が無意識のうちに変化し、
低脂肪な食品への好みが減る点です。
これはダイエット中の方や食習慣改善を目指す方にとって、
見えない落とし穴となり得る現象です。
もっとも、この研究は正常体重の成人を対象とし、観察期間も8週間と短いため、
肥満者や若年層、長期間の影響を含めた一般化にはまだ慎重さが必要です。
それでも「満腹でもつい食べたくなる」のは、意志の問題ではなく、
脳の報酬系が“学習”によって変化してしまった結果かもしれない——
この新たな視点は、これからの食事管理やダイエットにおいて、
非常に価値あるヒントになると感じています。