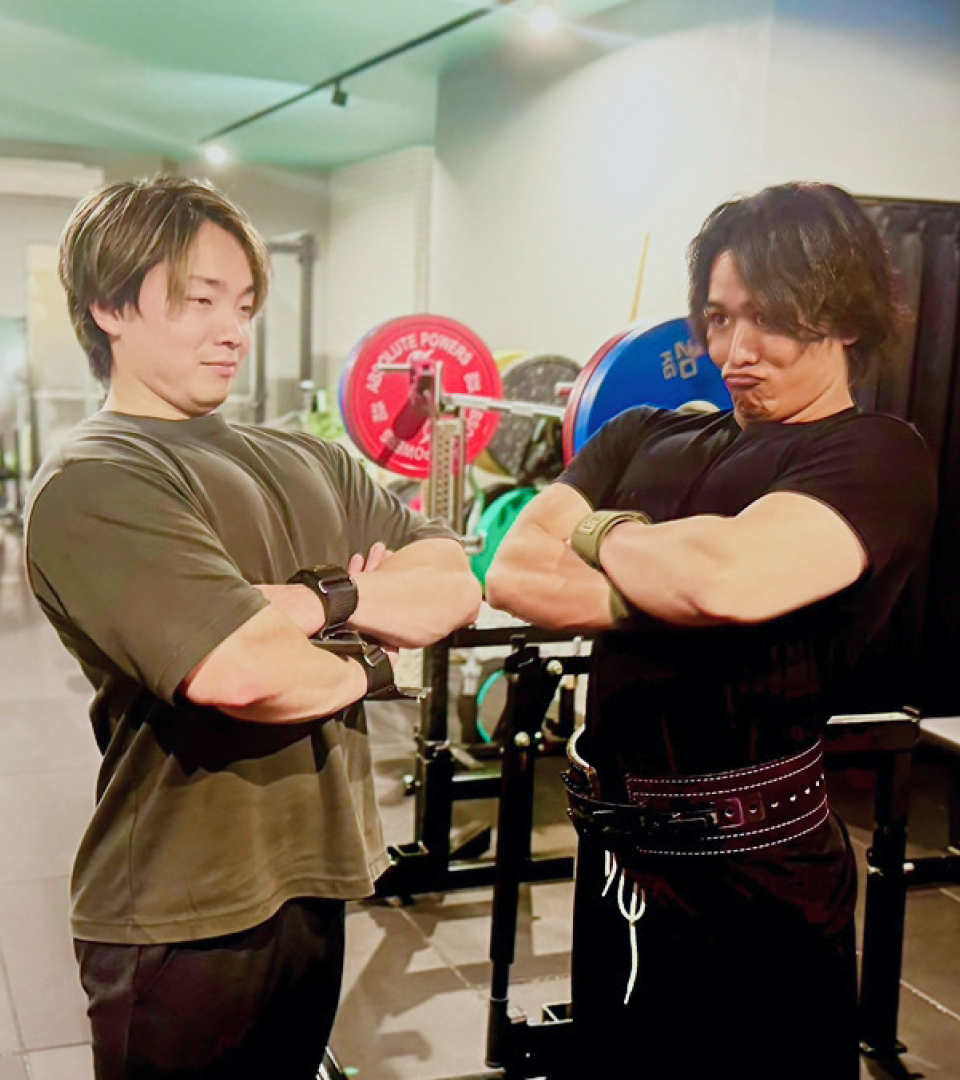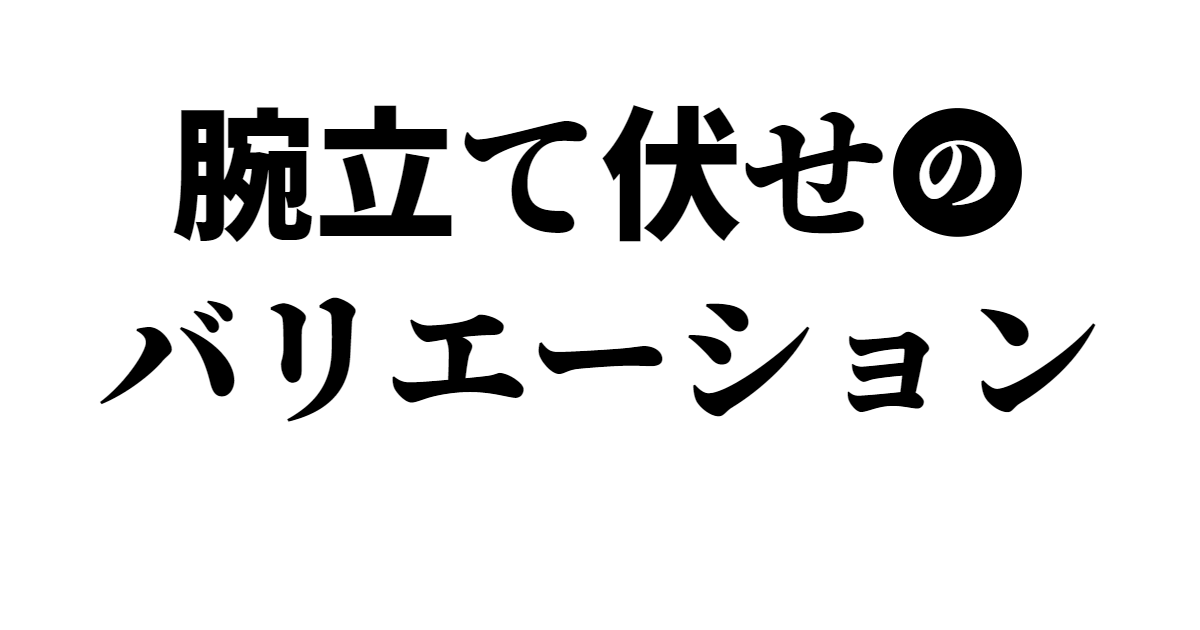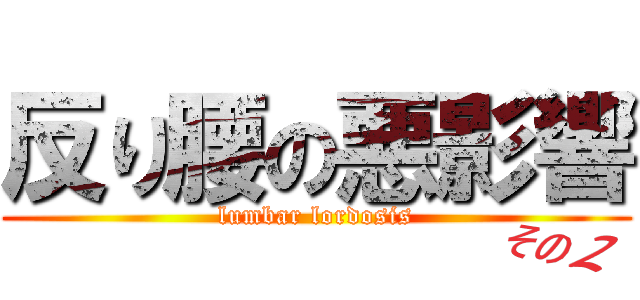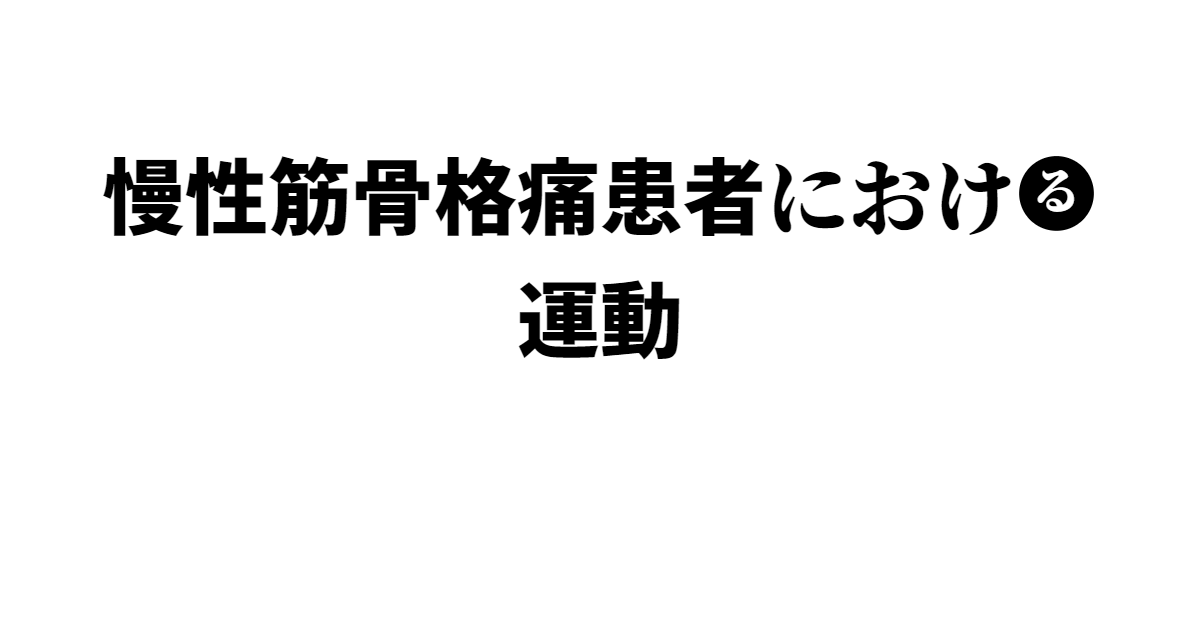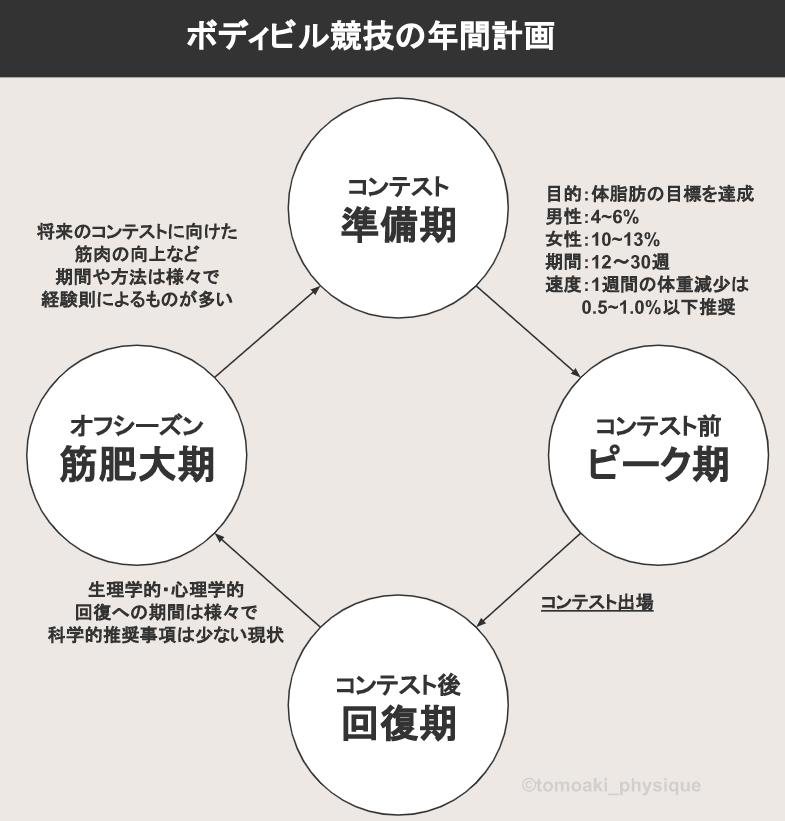2023.06.26
お風呂と温泉の違いについて
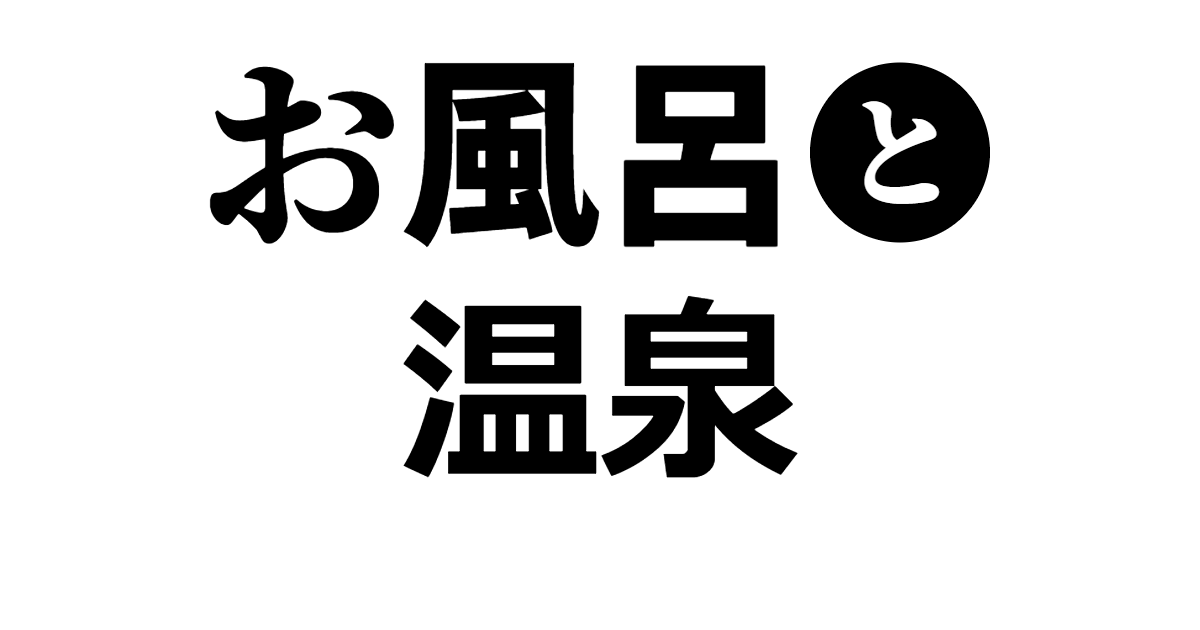
みなさまこんにちは。
パーソナルトレーナーの亀山です。
今回は、塩化ナトリウムと人工炭酸泉への曝露による
睡眠プロファイルの変化についての論文を引用していこうと思います。
論文
この研究の目的は、ナトリウム塩化物泉(SCS)と
人工炭酸泉(ACS)での入浴は、が体温と脳波に及ぼす影響を調べ、
睡眠を促進するかどうかを評価することを目的とした。
参加者は、健康な男性8名(平均年齢20.1歳)、地元のスパ付きホテルで、
1週間間隔でSCS、ACS、素湯(PHB)、または無入浴(NB)を受けた。
参加者は湯の特徴から入浴の種類を識別できるため、
参加者と研究者は入浴条件について盲検化されなかった。
温泉入浴による多くの健康効果は、古来より認められている。
特に様々なミネラル成分を含む温泉への入浴は、
身体を温めることで睡眠を促進し、改善することが知られている。
熱放散によって上昇した中核体温が低下し、
睡眠が促進されると推測されている。
しかし、脳波を用いたこれらの効果の科学的確認は限られている。
そこで、温泉が睡眠を促進するか、改善するかを確認するために、
温泉が中核体温と脳波に及ぼす影響を調べた。
本研究で使用した温泉の種類は、SCSとACSである。
SCSは日本では非常に一般的な泉質であり、
ナトリウム塩化物が皮膚に残り、入浴後も保温効果が高い。
湯野浜温泉(Na l,236mg/kg、K 629mg/kg、Cl 2,589mg/kg)において、
SCSによる身体加温の効果を次のように報告している。
・1回の入浴で体温、保温力、血流が上昇した。
・日間の入浴で、心理的なリラックス効果が認められた。
・本研究で使用した秋田温泉さとみもSCSであり、同様の体温上昇が観察された。
今回の研究では、入浴によって睡眠プロファイルを変化させる主な要因は、
遠位-近位温度勾配(DPG)の低下に伴う中核体温の上昇、次いで就寝時の中核体温の
大きな低下によって特徴づけられる体温変化であることがわかった。
SCSとACSでは、PHBと比較して、体温に対するより大きな効果が観察された。
このことは、以前に報告されたように、SCSのミネラル組成(すなわち、塩化ナトリウム)と
ACSのCO2が、熱吸収とそれに続く熱放散を促進することを
示唆しているのかもしれない。
体温の上昇と低下から、睡眠前の入浴のタイミングが重要であると考えられた。
入浴15分後、体温がベースラインに戻るまでに約90分かかり、
その後、体温はベースライン以下まで低下することが観察された。
40~42.5℃での入浴やシャワーは、就寝1~2時間前の
睡眠潜時を10分短縮し、自己評価による睡眠の質と効率を改善した。
これらは、末梢血流灌流の増加によって達成されるDPGと、
体温放散による中核体温の低下時間と一致すると考えられた。
研究結果も、このタイミングと湯温を概ね支持している。
したがって、今回の実験条件では、就寝90分前が睡眠を促す最適なタイミングであった。
興味深いことに、ACSはSCSと同様の体温変化を引き起こし、
どちらも同様に睡眠プロファイルの特徴を変化させたが、
ACSは入浴後の疲労を引き起こさなかった。
SCSの疲労感の違いは、化学組成の違いによる可能性もあるが、
その他の要因は他の入浴条件と同様であったと考えられる。
したがって、高齢者やその影響を受けやすい人には、
SCSよりもACSの方が適切であろう。
まとめ
ただのお湯よりも人工でも温泉系に入る方がいいみたいですね。
湯船入るのめんどくさいですけど、
睡眠に悪影響感じてる人は
試してみるのもアリだと思います。
お客様で睡眠取れなかった人が、
湯船入る日だけ寝れるようになったって人もいたので、
結構いいとは思います。
私は最近ほとんど入らないですけど。
過去おすすめ記事
・慢性痛と睡眠の関連性