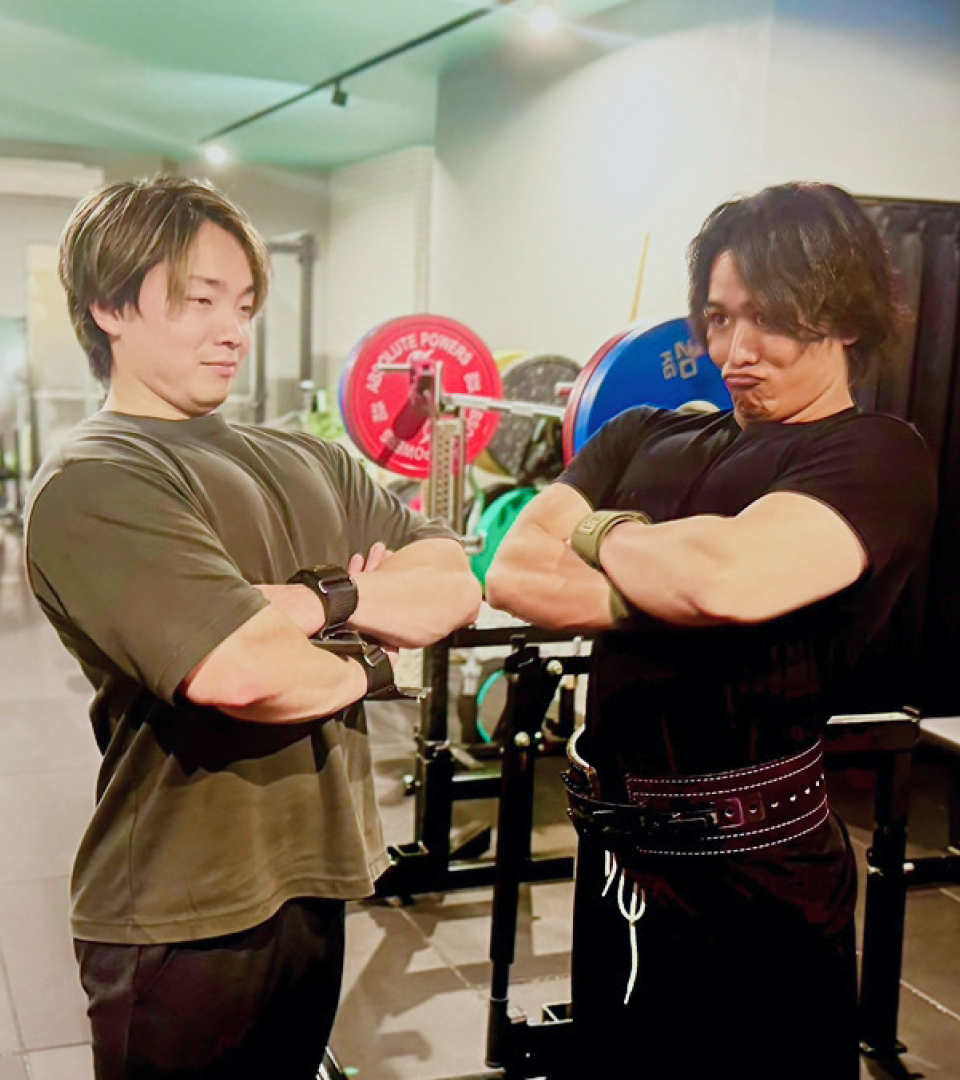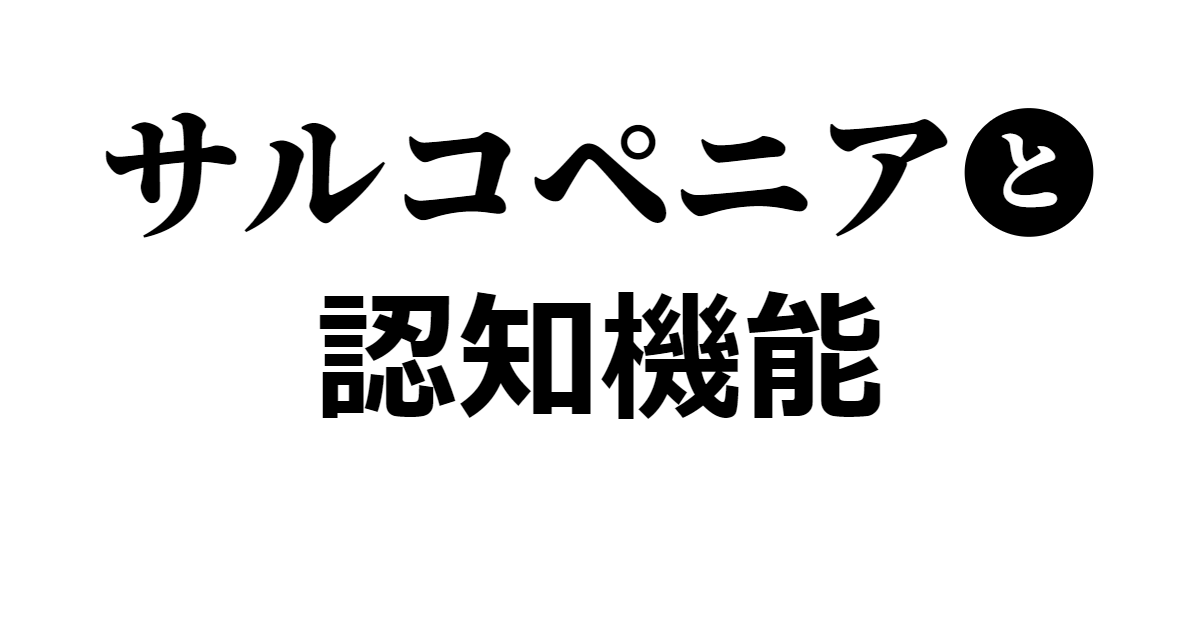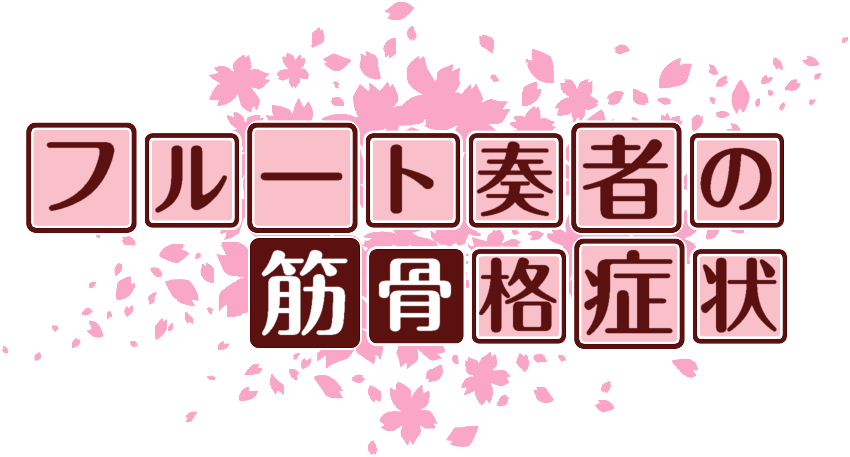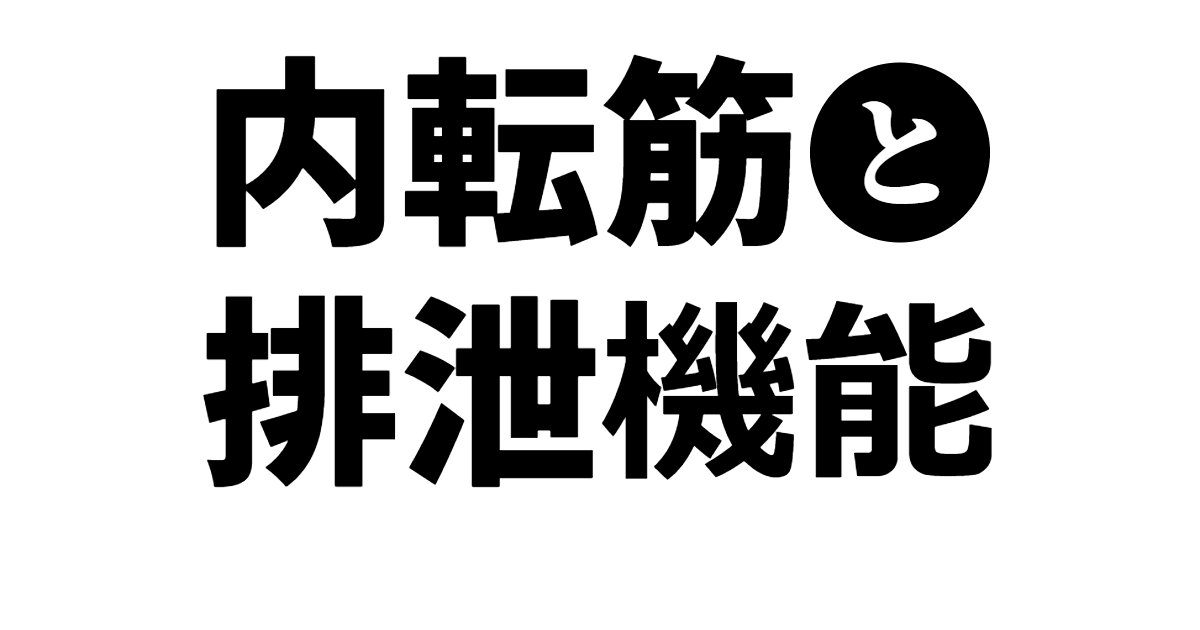2022.03.26
可動域の確保のためには?

みなさまこんにちは。
パーソナルトレーナーの亀山です。
今回は”ストレッチ”に関する論文を
ご紹介していこうと思います。
論文
静的ストレッチ(SS)、動的ストレッチ(DS)、筋膜フォームローリング(FR)が
股関節屈曲時の可動域に及ぼす影響を調べたものです。
長時間のSSは競技パフォーマンスを低下させる可能性があり、
FRは筋弛緩を引き起こし、筋機能、身体パフォーマンス、可動域(ROM)を
向上させる可能性がある。
本研究では、FR、SS、DS後のROMに対する
組織コンプライアンスの変化の単独影響について検討した。
若年成人男性14名に対して、
SS、DS、FR前後で、与えられた関節トルクにおける
股関節屈曲ROMを無作為に評価した。
股関節伸展筋2種の筋電図解析を行い、
ROM測定時の能動筋の寄与をコントロールした。
SSとDSでは有意なROMの増加が観察されたが、
FRでは観察されなかった。
SSおよびDSは腱及び筋組織への伸長力は
主に縦方向に作用するが、
FRでは主に横方向の力が誘発される。
したがってFRでのROMの増大は、
疼痛閾値の変化による可能性が高い。
まとめ
これだけ見て、FRのメリットがない!と決めつけるのは
よくある誤情報の発信者と同じになってしまいます。
FRでも疼痛閾値の変化でROMが変わるので、
閾値を変化させてからのSSは?DSは?
筋緊張が強過ぎて伸びない人は?など
まだまだ考える余地はあります。
論文などは基本、帰納法です。
その時点で100%と言えないことが分かると思います。
過去おすすめ記事
・ストレッチにおいて